災害による心理状態の変化
茫然自失期(数時間~数日間)
災害が発生した直後に見られる時期で、強いショックや恐怖、混乱により感情が麻痺し、呆然とした状態になることがあります。現実を受け入れきれず、何も感じられない、何も考えられないといった無反応の状態が続く場合もあります。
ハネムーン期(数日~数週間)
助かったことへの安堵感や、周囲との一体感・連帯感が高まる時期です。支援が届き、希望を持ちやすい反面、一時的な高揚感によって無理をしてしまう人も多く、疲労や心の反動が後から表れることがあります。
幻滅期(1か月~数か月)
支援の減少や現実の厳しさに直面し、不満や孤独感が強まる時期です。怒りや悲しみ、無力感が表れやすく、「誰も助けてくれない」「なぜ自分だけが」といった思いを抱きやすくなります。うつ症状や人間関係のトラブルが生じることもあります。
再建期(数か月~数年)
被災者が現実に向き合いながら生活再建へ踏み出す時期です。気持ちの整理が進み、徐々に日常を取り戻していきますが、不安や葛藤を抱えることもあります。支援者は長期的な視点で、回復を支える姿勢が求められます。
- PTSD:災害などによって生命の危機や強い恐怖を体験した後に生じる精神
- 二次受傷:被害者を支援する立場の人(支援者や家族など)が、話を聞くことで心理的に影響を受け、ストレスや不調を抱えること
災害時に活動する支援チームの種類と役割
DPAT(災害派遣精神医療チーム)
災害時に被災者の心のケアや精神科医療支援を行う専門チーム。
精神科医、看護師、精神保健福祉士などで構成される。
DMAT(災害派遣医療チーム)
災害発生直後に現場で救命医療を行う専門チーム。
医師、看護師、薬剤師などが参加し、急性期医療を担う。
DWAT(災害派遣福祉チーム)
避難所などで高齢者や障害者など要配慮者への支援を行う福祉チーム。
社会福祉士、介護職、保健師、行政職員などで構成される。
その他
- DHEAT:災害時健康危機管理支援チーム
- JMAT:日本医師会災害医療チーム
- JDAT:日本歯科医師会災害支援チーム
- JVOAD:全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
被災者に対する心理的支援
サイコロジカルファーストエイド(PFA)
災害や事故の直後に用いられる心の応急手当。
被災者の安全・安心を確保し、落ち着きを取り戻すための支援を行う。話を無理にさせるのではなく、「そばにいる・話を聴く・必要な支援につなぐ」ことを重視します。
特徴
- 専門資格がなくても対応可能(誰でもできる支援)
- 無理に体験を語らせない(再トラウマの防止)
- 安全・安心・つながり・実用的な支援がキーワード
心理的デブリーフィング
災害や事故、犯罪被害などの強い心理的ショックを受けた人々に対して、体験直後の急性期に行われる心理的援助の手法です。
トラウマとなる出来事を体験した人が、その体験や当時の感情を語り合い、ストレスや不安を緩和することを目指しますが、有効性がないことがすでに実証されており、国際的にも推奨されていません。
トリアージ
災害や事故などの多傷病者が同時に発生した場面で、治療や搬送の優先順位を判断するための選別行為のことです。
限られた医療資源の中で、助かる可能性の高い人から優先的に治療を行うことで、全体の救命率を高めることを目的としています。
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
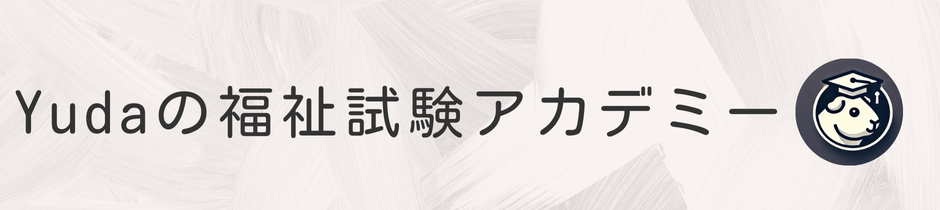
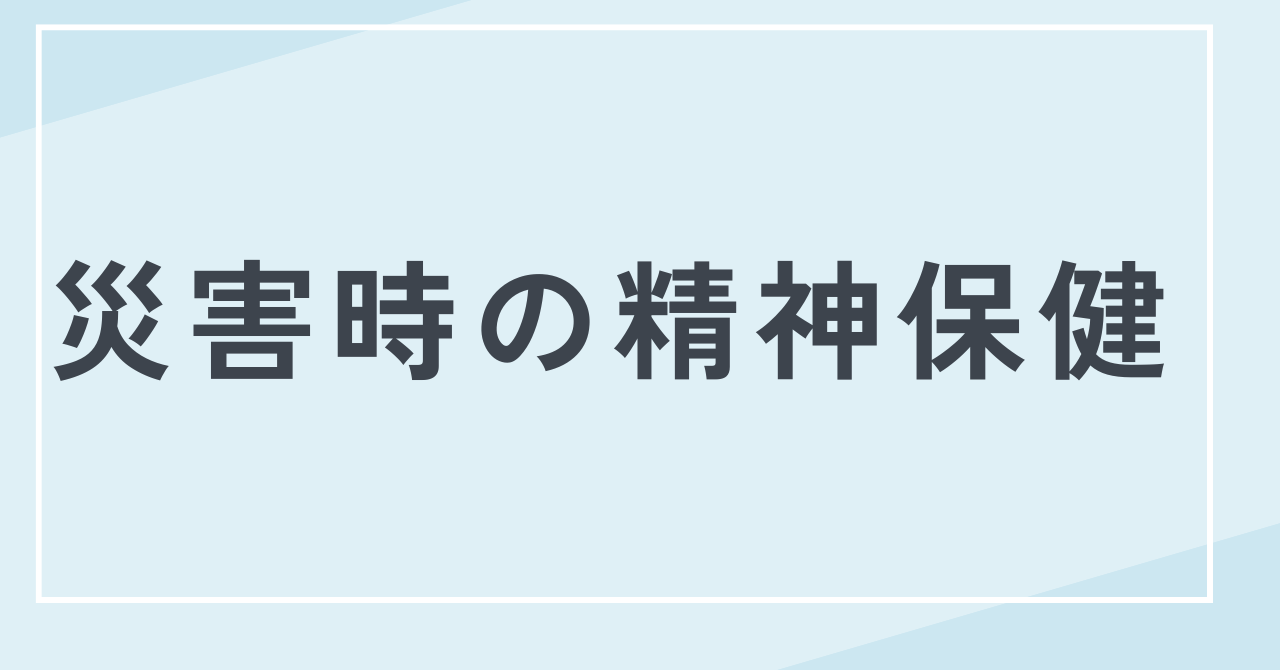
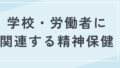
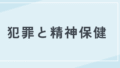
コメント