DV
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
DVとは、親密な関係にある者(配偶者・恋人など)から受ける暴力のことをいいます。
DV防止法における適用の対象
- 配偶者(事実婚含む) → 対象〇
- 元配偶者 → 対象〇
- 同居中の交際相手 → 対象〇
- 同居していた交際相手 → 対象〇
- 同居歴のない交際相手 → 対象外×
※ただし、「交際相手」への暴力はストーカー規制法や刑法(暴行罪等)で対応可能
暴力の種類(相談の対象となり得るもの)
- 身体的暴力:殴る・蹴る・物を投げつける
- 精神的暴力:罵倒する・無視する・脅迫する
- 性的暴力:性行為の強要・避妊拒否
- 経済的暴力:生活費を渡さない・働かせない
- 社会的暴力:交友関係の制限・監視
面前DV:子どもが家庭内でDVを「目撃」または「同じ空間で体験」すること。
子どもの発達や精神的安定に深刻な影響を及ぼします。
→児童虐待防止法でも「心理的虐待」として定義されています
配偶者暴力相談支援センター
- 根拠法:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)
- 制定年:2001年(平成13年)
- 設置主体:都道府県(義務)/市町村(努力義務)
- 役割:DV被害者に対して、相談対応・一時保護・自立支援などを行い、警察や医療、福祉機関との連携によって支援体制を整える。
出産・育児
出産や子育ては、人生のなかでも喜びと同時に大きな心理的変化やストレスを伴うライフイベントです。
出産期
- マタニティーブルーズ:出産後3~10日頃に見られる一時的な情緒不安定で、自然に軽快します。
- 産後うつ病:出産後数週間~数か月以内に発症する抑うつ気分や育児への無力感で、治療が必要な場合があります。
- 産褥期精神病:出産後まもなく発症する重度の精神障害で、幻覚や妄想を伴い、入院が必要になることもあります。
育児困難と虐待リスク
- 育児に自信が持てない、孤立感、不安の強まり → 虐待のリスク増大
- ネグレクト(育児放棄)や心理的虐待など、支援につながらないと深刻化する可能性あり
- 家族支援や育児支援機関との早期連携が重要
児童虐待
- 身体的虐待:子どもに対して殴る、蹴る、物を投げつけるなどの暴力をふるう
- 心理的虐待:言葉や態度などで子どもの心を傷つける行為
- ネグレクト(放置・放任):衣食住、医療、教育などの必要なケアを怠る
- 性的虐待:子どもに対してわいせつな行為をする・させる、または見せる
介護
介護は身体的・時間的負担だけでなく、精神的ストレスや孤立感を伴いやすいです。
よく見られる心理状態
- 介護うつ(無力感・抑うつ・不眠)
- 怒りや罪悪感の交錯
- 燃え尽き症候群(バーンアウト)
- 誰にも相談できない孤立状態
高齢者虐待
- 身体的虐待:殴る・叩く・ベッドに縛る
- 心理的虐待:侮辱・無視・威圧的な言葉
- 性的虐待:性的な行為・接触を強要する
- 経済的虐待:年金を勝手に使う・使わせない
- ネグレクト:排泄物を放置・食事を与えない
セルフネグレクト
自分自身の健康や安全、生活環境に対する関心や管理を放棄し、生活に支障をきたす状態を指し、高齢者に多く見られます。
〇特徴
- 生活環境の悪化:掃除や洗濯、ゴミ出しができず、住居が不衛生になる。
- 健康管理の放棄:適切な食事や医療を受けない。
- 社会的孤立:家族や地域社会とのつながりが希薄化。
- 心理的要因:無気力や無関心が顕著。
セルフネグレクトは他者への危害ではなく自己放任に起因するため、高齢者虐待防止法の対象外となる場合もありますが、栄養失調や感染症などの健康問題が生じやすく、孤独死のリスクも高まるため、適切な支援が重要です。
ヤングケアラー
本来大人が担うような家事や家族の世話・介護・感情的サポートを日常的に行っている、主に18歳未満の子どもを指します。
〇具体的なケア内容の例
- きょうだいの世話や家事全般
- 障害や病気のある家族の介護
- 親の代わりに金銭管理や通訳
- 精神疾患のある家族の感情的支え
ひきこもり
ひきこもりの定義
様々な要因の結果として社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態です。
主な背景要因
- 発達障害やうつ病、統合失調症などの精神疾患
- いじめ、不登校、就労失敗などの挫折体験
- 家族関係の問題(過干渉、依存関係)
- 経済的困窮、社会的孤立
ひきこもり地域支援センターの概要
- 根拠法: 「ひきこもり対策推進事業」に基づき、厚生労働省が推進。
- 実施主体:都道府県・指定都市・市区町村(民間団体への委託可)
- 役割:ひきこもり状態にある本人や家族への支援を行い、自立や福祉の増進を図る。
ひきこもり支援コーディネーターを2名以上配置
(1名は社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士などの専門職)
喪失体験
グリーフケア
グリーフとは、大切な人や存在を失ったことに伴う深い悲しみや苦痛のことを指します。死別だけでなく、病気、離別、失業など人生のさまざまな喪失にも関連します。
グリーフケアとは、グリーフに苦しむ人に対して、心理的・社会的に寄り添い、適応を支援するケアのことです。
喪失反応モデル
- 提唱者:エンゲル
- 対象:喪失体験全般(死別・身体機能の喪失など)
- 段階数:4段階
- 主な内容:ショックと否認 → 悲しみ・不安・怒り → 意識化と表面的受容 → 復元
死の受容過程
- 提唱者:キューブラー・ロス
- 対象:終末期の患者
- 段階数:5段階
- 主な内容:否認 → 怒り → 取引 → 抑うつ → 受容
複雑性悲嘆
喪失から長期間たっても強い悲しみや苦痛が続き、日常生活に支障をきたす状態のこと。
通常の悲嘆反応を超えており、専門的支援や治療が必要となる場合があります。
予期しない突然の喪失や子どもの死、周囲からのサポートが得られない場合などに陥ることが多くなります。
予期悲嘆
死や喪失が起こる前から感じる悲しみや苦しみのことを指します。本人だけでなく、周囲の人も経験する可能性があります。
実際の死別時の衝撃を緩和し、悲嘆プロセスの準備を促す役割もあります。
その他
共依存
共依存とは、依存関係にある相手を支え続けることで自分の存在価値を感じる状態を指します。特にアルコール依存症やDVの家庭で、支配的・犠牲的な関係に家族が巻き込まれやすく、精神的負担が大きくなることがあります。共依存は無意識に繰り返されることが多く、支援者による関係性の理解と介入が求められます。
カサンドラ症候群
カサンドラ症候群とは、発達障害、特にASD(自閉スペクトラム症)のパートナーをもつ人が、周囲に理解されず孤立し、強いストレスや抑うつ状態に陥ることを指します。正式な医学的診断名ではありませんが、実際には支援が必要なケースが多く、家族の苦しみに目を向ける視点が重要とされています。
アダルトチルドレン
アダルトチルドレンは、機能不全家族、たとえばアルコール依存症の親や虐待、過干渉のある家庭で育ち、大人になってもその影響を引きずる人を指します。人間関係に不安を感じやすく、自己肯定感が低い傾向があります。
8050問題
8050問題とは、80代の親が50代の子ども、特に長期ひきこもり状態にある子を支え続けている家族の問題です。親が高齢化する中で、介護や死亡によって家庭が機能しなくなるリスクが高く、生活困窮や社会的孤立など、複合的な課題を抱えやすいのが特徴です。地域福祉、精神保健、就労支援など多方面からの連携が求められています。
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
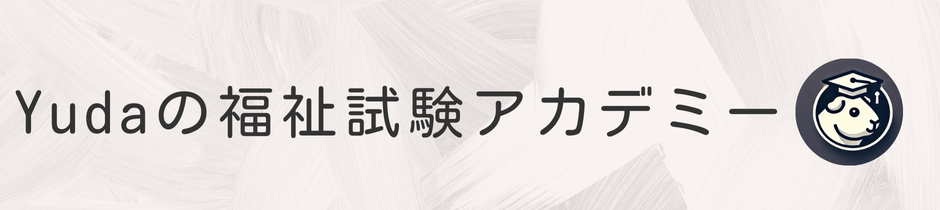
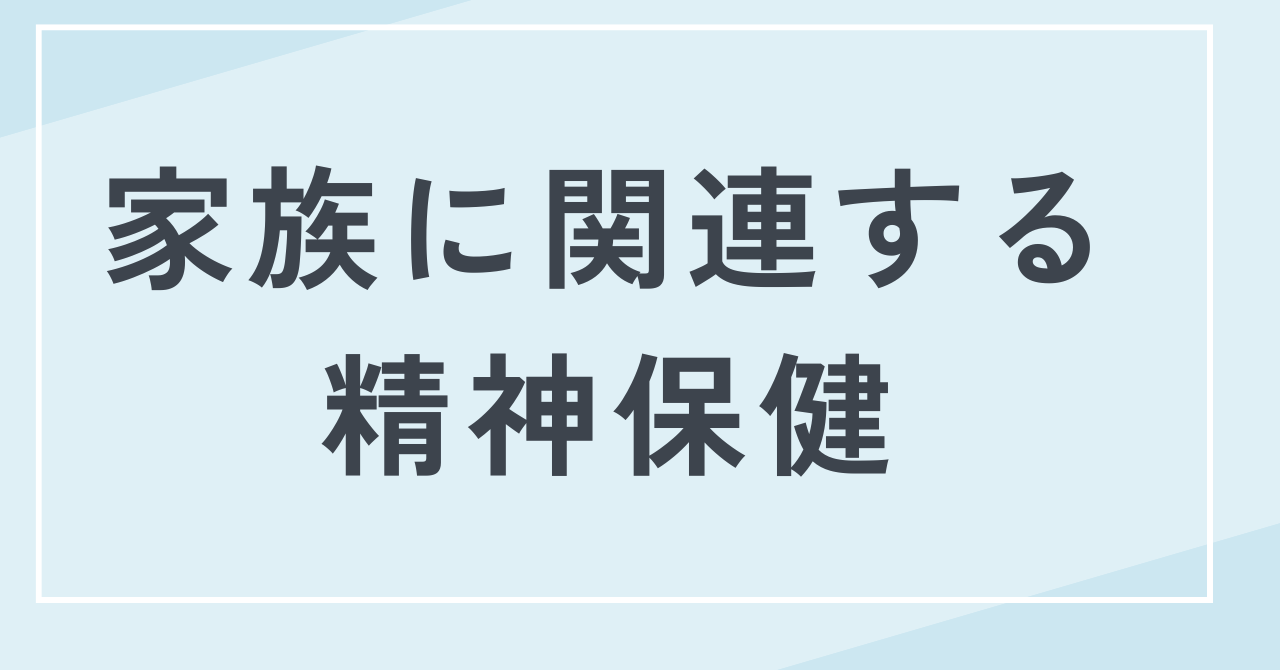
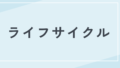
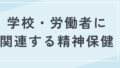
コメント