社会的手抜き
集団での作業において、他の人に任せられるという意識から、個人の努力量が低下する現象。リンゲルマン効果とも呼ばれます。
社会的抑制
他者が存在する場面で、緊張や不安から本来の能力を発揮できず、パフォーマンスが低下する現象。特に慣れていない課題や複雑課題で起きやすいです。
社会的促進
他者が見ていることで、やる気や集中力が高まり、パフォーマンスが向上する現象。特に習熟した課題や単純作業で効果が現れやすいです。
社会的ジレンマ
個人の利益を優先すると、結果的に集団全体が不利益を被る状況。環境問題や公共財の利用などが例として挙げられます。
同調行動
多数派の意見や態度に合わせて、自分の意見や行動を変えること。アッシュの実験が有名で、間違っていると分かっていても多数に合わせる傾向が示されました。
集団極性化
集団での話し合いを経て、意見がより極端な方向に偏る現象。
コーシャスシフト:集団での話し合いを通じて、より慎重な判断に偏る傾向。リスク回避的な方向に意見が変化します。
リスキーシフト:集団での話し合いを通じて、より大胆な判断に偏る傾向。リスクを積極的に取ろうとする方向に意見が変化します。
内集団バイアス
自分が所属する集団(内集団)を過大評価し、他の集団(外集団)を過小評価する傾向。偏見や差別の一因となります。
集団浅慮
集団の合意を優先しすぎて、現実的で合理的な判断ができなくなる現象。グループシンクとも呼ばれ、異論を排除する傾向が強まります。
集団凝集性
集団の一体感や結束力の強さを指します。凝集性が高いほど協力的になりますが、時に集団浅慮の原因にもなり得ます。
スケープゴート
集団内の問題や不満のはけ口として、特定の人物や集団に責任を押し付けること。差別やいじめの要因となることがあります。
集団規範
集団内で共有されている暗黙のルールや期待される行動様式。成員はこの規範に従うことで、所属意識や秩序が保たれます。
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)


試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
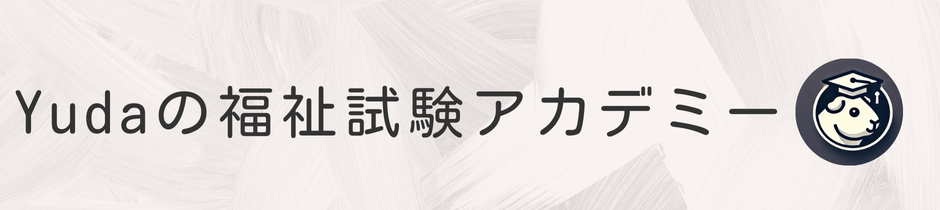

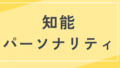
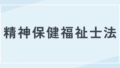
コメント