統合失調症は精神保健福祉士を目指すうえで1番といってもいいほど知っておくべき病気です。
10代後半から30代に多く見られる妄想や幻覚、まとまりのない発語などの症状が特徴的な病気で入院患者数の最も多い精神疾患です。
陽性症状と陰性症状
陽性症状
通常の精神機能に「付加」される症状のことを指します
健康な人にはないもの(幻覚や妄想など)がある
陰性症状
通常の精神機能が「欠如」または「低下」した状態を指します
健康な人にあるもの(意欲や感情など)がない
4つの病型
妄想型
幻覚・妄想が中心で最も多い病型
他の病型に比べ発症年齢が遅く、30代前後に発症しやすいのが特徴です
破瓜型(解体型)
感情の平板化(喜怒哀楽の消失)、意欲の低下、発動性の低下といった症状が中心の病型
思春期から青年期に発症することが多いのが特徴です
予後が悪い
緊張型
突然大声を上げるなどの激しい興奮状態(緊張病性興奮)と、周囲への反応が極端に鈍くなる昏迷状態(緊張病性昏迷)という正反対の状態がみられる病型
回復は早いが再発しやすいのが特徴です
単純型
陰性症状が中心となる病型
主な症状について
知覚障害
幻覚・・・外部からの実際の刺激がないにもかかわらず、知覚として体験される現象。
特に幻聴が多い。他に幻視や体感幻覚(体の内部や表面で異常な感覚を感じる幻覚)など
錯覚・・・現実に存在するものを誤って知覚する現象。
思考障害
- 妄想
論理的な説明や事実と合わないにもかかわらず、本人が強く信じ込んでいる誤った信念
代表的な妄想とその例
被害妄想:「誰かに監視されている」「嫌がらせを受けている」
誇大妄想:「自分は特別な能力を持っている」「世界を救う使命がある」
注察妄想:「周囲の人が自分を見て笑っている」「テレビが自分のことを話している」
心気妄想:「自分の体が腐っている」「重い病気にかかっている」
関係妄想:「周囲の出来事がすべて自分と関係がある」
一次妄想:全く根拠を持たない妄想
二次妄想:状況、体験、感情などからある程度心理的に了解できる妄想
思路の障害
- 思考途絶:思考が突然止まってしまう状態
- 連合弛緩:思考のまとまりが悪く、言葉の意味関係が乱れている状態
- 滅裂思考:連合弛緩が重度化し、思考のまとまりが極端に失われ、話がバラバラで意味不明な状態
自我障害
- させられ体験(作為体験):自分の意思とは関係なく、思考や行動が外部から操作されていると感じる
- 離人症:自分自身や周囲の世界が現実感を失い、異質なものに感じられる状態
- 考想化声:自分の考えがあたかも他者の声になって聞こえる現象
感情・意欲の障害
- 感情鈍麻:感情の反応が乏しくなり、喜怒哀楽が薄れる
- 無為自閉:自発的な行動や意欲が著しく低下し何もしなくなったり、外部との関わりを避け、引きこもるようになる
- 両価感情:相反する感情を同時に抱き、どちらの感情も捨てられずに葛藤する状態
シュナイダーの一級症状
ドイツの精神科医シュナイダーは統合失調症の診断上特に重要な症状を一級症状としてまとめています
- 考想化声
- 対話形式の幻聴
- 自己の行為に随伴し口出しする形の幻聴
- 身体への影響体験
- 思考奪取
- 考想伝播
- 妄想知覚
- させられ体験
統合失調症の治療
統合失調症の治療は、主に薬物療法と精神社会的療法を組み合わせて行います。症状の改善だけでなく、社会復帰や再発予防も大切な目的です。
薬物療法
治療の基本は抗精神病薬の服用です。幻覚や妄想などの陽性症状を抑える効果があり、再発の予防にも有効です。近年は副作用が少ない非定型抗精神病薬がよく用いられます。服薬を継続することで、症状の安定と再発の予防が期待できます。
精神社会的療法
薬だけでなく、心理教育、生活技能訓練(SST)、カウンセリング、リハビリテーションなどの支援も重要です。
- 心理教育:病気の正しい理解を深め、再発予防や服薬の大切さを本人や家族と共有します。
- SST(社会生活技能訓練):人とのやり取りや感情のコントロールを練習し、対人関係の力を高めます。
- 就労支援や作業療法なども行われ、社会生活への復帰を目指します。
入院と外来の治療
急性期には症状が強いため、安全確保のために入院が必要となることもあります。症状が落ち着いた後は、外来での通院治療を継続しながら、地域での生活を支えていきます。
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
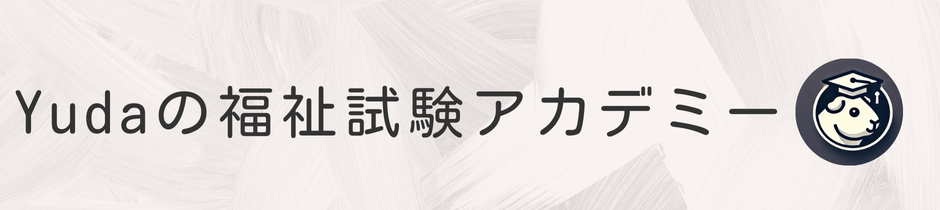
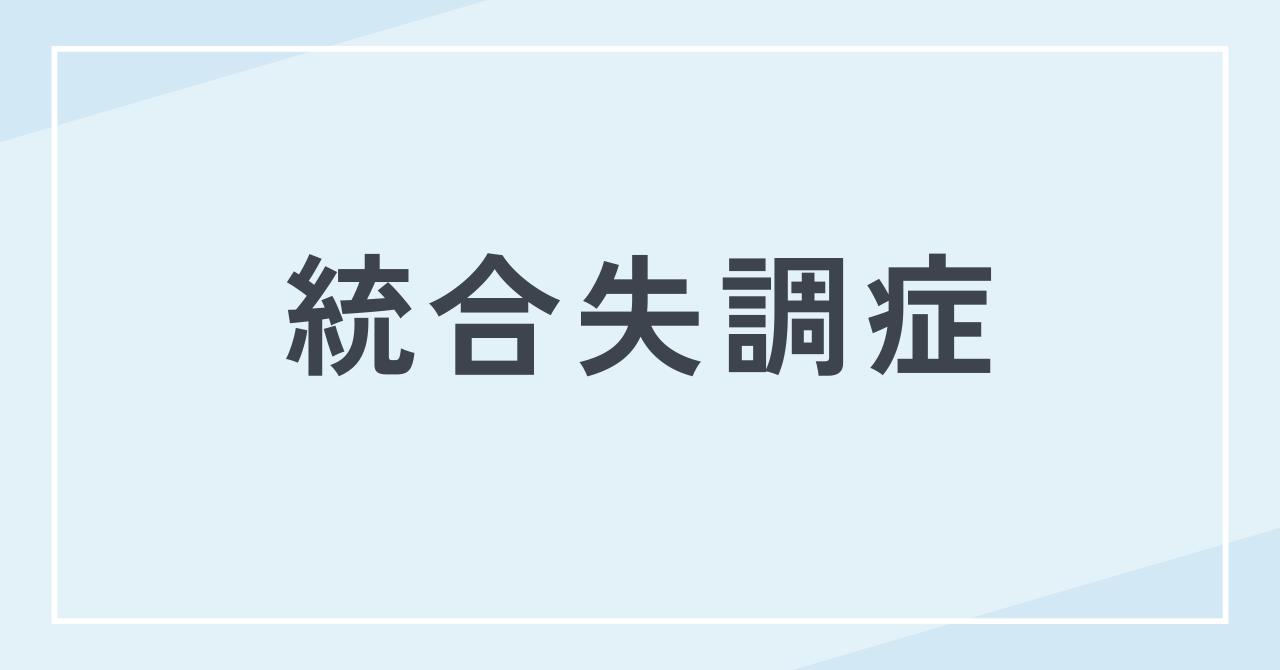
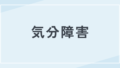
コメント