ここでは代表的な精神療法についてまとめています。
目次
精神分析療法
フロイトの理論に基づき、無意識の葛藤を探り、過去の体験や抑圧された感情に気づくことで症状を改善する療法です。
自由連想 患者が思いつくままに言葉を発し、その連想の流れから無意識の内容を明らかにする技法です。
夢分析 夢の象徴的な意味を解釈し、抑圧された欲望や葛藤を探る技法です。
フロイトは、夢の意味を深く理解するために自由連想を用いることが重要だと考えました。患者が夢の内容について自由連想を行うことで、夢に隠された無意識の心理的要素を明らかにできるとしました。
精神力動的精神療法
無意識の力動(心の動き)に焦点を当て、過去の経験や人間関係が現在の心理的な問題にどのように影響を与えているかを理解し、解決を目指します。
精神分析療法との違い
- 精神分析よりも治療期間が短く、頻度も少ないことが多い。
- 患者が寝椅子に横になるのではなく、治療者と向かい合って座って話すことが多い。
- 転移や逆転移の解釈に加えて、患者の現在の問題や人間関係にも焦点を当てる。
転移と逆転移
精神力動的精神療法では、転移と逆転移が治療過程において重要な役割を果たします。
転移
患者が過去の重要な人物(親や兄弟など)に抱いていた感情や態度を、治療者に向ける現象。
治療者を「理想の父親」と思い込み、強い信頼を寄せる(陽性転移)
治療者を「厳しい母親」と重ね、反発する(陰性転移)
逆転移
治療者が患者に対して、無意識のうちに自分の過去の感情を投影する現象。
患者を自分の子どもと重ね、過保護になってしまう
患者に強い苛立ちを感じ、冷たい態度を取ってしまう
治療の中で転移を適切に扱うことで、患者の無意識の葛藤を明らかにし、解決へ導くことができます。また、治療者は逆転移に気づき、適切にコントロールすることが求められます。
認知療法
ベックが提唱。
歪んだ思考(認知の歪み)を修正し、現実的で柔軟な考え方を身につける療法。
行動療法
学習理論に基づき、不適応な行動を修正し、適応的な行動を増やすことを目的とした療法。
認知行動療法
認知療法と行動療法を組み合わせた療法。考え方の修正と行動の変容を同時に行います。
森田療法
森田正馬(もりた まさたけ)が創始した神経症(不安障害、強迫性障害など)の治療法です。
「あるがまま」の受容を重視し、不安や恐怖をなくそうとせずに、それを受け入れながら行動を続けることで、症状の改善を目指します。
入院治療の場合、「絶対臥褥期 → 軽作業期 → 重作業期 → 退院準備期」の4つの段階を経て回復を目指します。それぞれの段階には目的があり、不安を受け入れながら徐々に日常生活へ適応していくプロセスを踏みます。
絶対臥褥:患者がベッドで安静に過ごし、外部刺激を最小限にする期間です。会話や読書、スマホの使用などを禁止し、不安や症状と向き合いながら「あるがまま」を受け入れることを学びます。最初は退屈や不安が強まることもありますが、徐々に心が落ち着き、次の段階へ進む準備となります。
内観療法
吉本伊信によって創始された日本独自の心理療法です。自己の内面を深く見つめ、自己洞察を深めることで、心理的な問題の解決や自己成長を促すことを目的としています。
以下の3つの観点を中心に振り返ります。
〇「世話になったこと」(自分が相手から受けた恩)
例:「親がどれだけ自分のために尽くしてくれたか」「友人が支えてくれたこと」
〇「して返したこと」(自分が相手に対してした貢献)
例:「親に感謝を伝えたことがあったか」「周囲の人にどれだけ助けたか」
〇「迷惑をかけたこと」(自分が相手に与えた負担や迷惑)
例:「自分の行動で誰かを傷つけたこと」「相手を困らせたこと」
これらを振り返ることで、自分の考え方や行動を見直し、感謝や責任の意識を高めることが内観療法の目的です。
系統的脱感作法
不安や恐怖を段階的に克服するための行動療法の一種です。主に恐怖症や不安障害の治療に用いられ、不安を感じる状況に少しずつ慣れることで、恐怖反応を弱めていきます。
自律訓練法
ドイツの精神科医 シュルツが開発した、リラクゼーション法の一種です。
自己暗示を用いて心身をリラックスさせ、ストレスや自律神経の乱れを整える効果があります。
曝露療法(エクスポージャー法)
恐怖や不安を感じる状況に意図的に直面し、少しずつ慣れていくことで症状を克服する行動療法の一種です。回避行動を減らし、不安が軽減されることを体験することで、恐怖や不安への耐性を高めます。
モデリング法
他者の行動を観察し、それを模倣(モデル化)することで、新しい行動やスキルを習得する行動療法の一種です
トークンエコノミー法
望ましい行動を強化するために「トークン(代用通貨)」を報酬として与え、行動の変容を促す行動療法の一種です。トークンは一定数集めると、特典や報酬と交換できます。
ゲシュタルト療法
「今ここ(現在の瞬間)」に意識を向け、自分の感情や身体感覚を深く感じ取ることを重視する療法です。
ドイツ語で「ゲシュタルト」は「全体」や「形」を意味し、過去や未来にとらわれず、「今」の体験を統合し、自分らしい生き方を見つけることを目的としています。
心理教育
患者や家族に対して、精神疾患や治療について正しい知識を提供し、病気との向き合い方や対処方法を学ぶ支援のことです。病気を理解し、適切な対応を取ることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質(QOL)を向上させることが目的です。
箱庭療法
ミニチュアの人形や建物、動物、自然物などを使って箱の中に自由に世界を作ることで、内面の感情や無意識を表現し、心理的な安定を促す心理療法です。
心理劇(サイコドラマ)
即興演劇を用いて、自分の感情や問題を表現し、気づきや解決のヒントを得る心理療法です。実際に役を演じることで、内面の葛藤を客観的に見つめ、新たな視点を得ることができます。
遊戯療法(プレイセラピー)
主に子どもを対象に、遊びを通じて感情や葛藤を表現し、心の成長を促す心理療法です。言葉での表現が難しい子どもが、おもちゃや人形、絵、砂遊びなどを使って無意識の感情を表現し、心理的な安定を得ることを目的とします。
芸術療法
絵画・音楽・ダンス・演劇・詩などの芸術活動を通じて、感情や無意識の心理状態を表現し、心のケアを行う心理療法です。言葉での表現が難しい場合でも、創作活動を通じて自己表現ができるため、ストレスの軽減や心理的な安定を促す効果があります。
来談者中心療法
アメリカの心理学者ロジャーズが提唱。
クライエントの主体性を尊重し、治療者が指示やアドバイスをせず、共感的に寄り添うことを重視する心理療法です。
家族療法
家族を1つのシステムとして捉え、個人の問題を単独の症状としてではなく、家族全体の相互作用の結果として理解し、関係性の調整を通じて問題を解決する心理療法です。家族内の役割やコミュニケーションのバランスを見直し、適切な関係を築くことで、個人の心理的な安定や成長を促します。
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
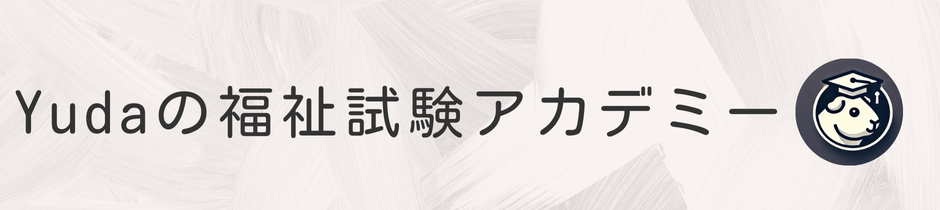
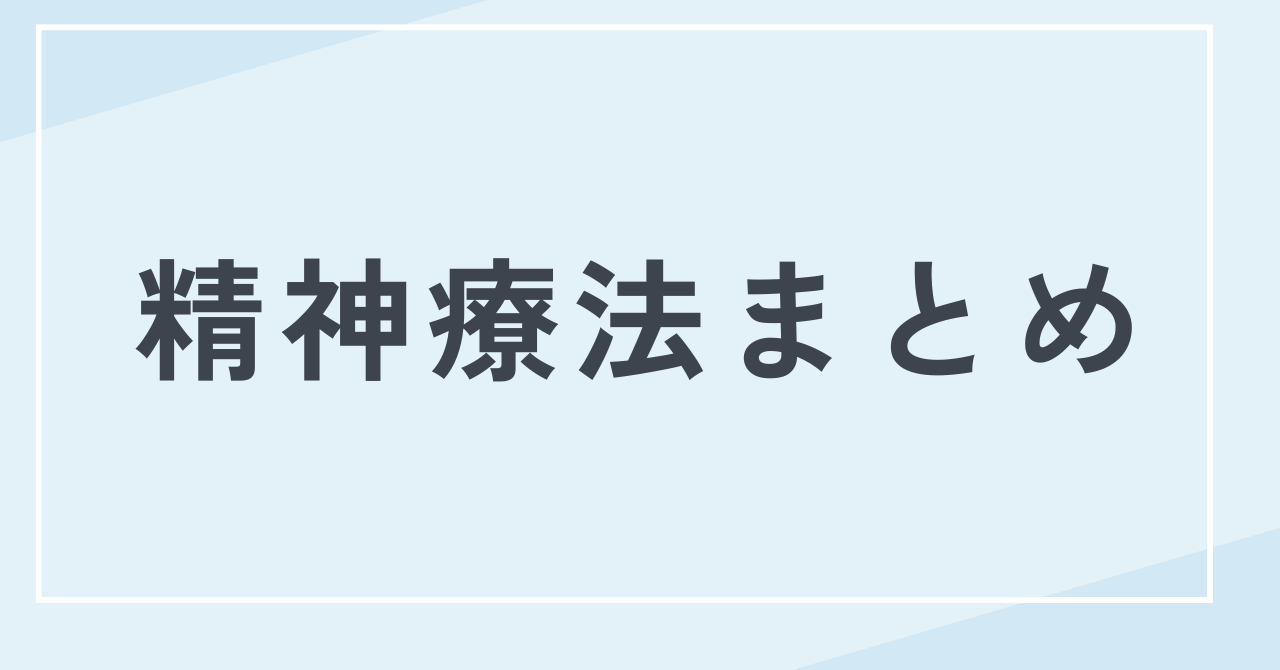
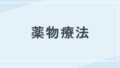
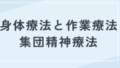
コメント