身体療法(脳刺激法)
精神疾患の身体療法は、薬物療法や心理療法とは異なり、脳や神経に直接的な影響を与える治療法です。主に重度の精神疾患や薬物療法が効果を示さない場合に用いられることが多いです。
電気けいれん療法(ECT)
脳に短時間の電気刺激(100ボルト前後)を与えて意図的にけいれんを誘発し、精神疾患の症状を改善する治療法です。
薬物療法や精神療法で効果がみられなかった症例に対して行われることが多く、第一選択肢として挙がることは少ないです。
治療の流れ
①前処置(事前準備)
・全身麻酔と筋弛緩剤を使用し、患者の安全を確保
・治療前に血圧・心拍数・脳波などをチェック
②電気刺激の実施
・頭部の電極を通じて脳に電流を流し、数十秒間のけいれんを誘発
・けいれんは脳内で発生し、外見上の動きは最小限に抑えられる
③回復期
・数分以内に意識が戻り、しばらく休息
・数回(通常6~12回程度)のセッションを行い、効果を確認
🔹 メリット
- 薬物療法よりも即効性がある(特に自殺リスクが高い場合に有効)
- 妄想や幻覚、重度の抑うつ症状の改善が期待できる
- 妊娠中のうつ病や薬剤が使えない場合でも実施可能
🔹 副作用・リスク
- 一時的な記憶障害(数時間~数日間の記憶が抜けることがある)
- 頭痛、筋肉痛などの軽度な身体症状
経頭蓋磁気刺激法(TMS)
強い磁場を使って脳の特定の部位に刺激を与え、神経活動を調整する非侵襲的な治療法です。うつ病の治療に特に有効とされ、薬物療法が効かない場合の選択肢として用いられます。
治療の流れ
①準備
患者はリクライニングチェアに座り、リラックスした状態で治療を受ける
頭部にTMS装置を装着
②磁気刺激の実施
強い磁場を発生させ、脳の前頭前野(特に左背外側前頭前野)に刺激を与える
1回の治療は約30~40分、1日1回を数週間継続
③治療後
すぐに通常の生活に戻ることができる(麻酔は不要)
🔹 メリット
- 麻酔なしで利用することができるため電気けいれん療法よりも容易に行うことができる
- 副作用が少なく、記憶障害のリスクがない
- 治療後すぐに日常生活に戻れる
🔹 副作用・リスク
- 軽度の頭痛や刺激部位の違和感
- 治療中の不快感(磁気パルスによる軽いピリピリ感)
- まれにけいれん発作を誘発する可能性がある(てんかん患者には慎重に適用)
作業療法
日常生活や社会活動に必要なスキルを回復・向上させるために、作業(手作業、運動、創作活動など)を通じて行うリハビリテーションです。精神疾患の患者に対しては、生活リズムの回復、社会適応力の向上、ストレス軽減などを目的として実施されます。
精神科作業療法の主な目的
✅ 生活リズムの安定化
精神疾患により崩れがちな生活リズム(昼夜逆転、活動意欲の低下など)を整える
例:「毎日決まった時間に活動を行い、生活習慣を改善する」
✅ 社会適応能力の向上
対人関係のトレーニングや、集団での活動を通じて、社会生活に必要なスキルを身につける
例:「グループ活動を通じて他者と協力する力を養う」
✅ ストレス管理と感情調整
創作活動や軽作業を通じて、リラックスしながらストレスを軽減する
例:「編み物や塗り絵をすることで、気持ちを落ち着かせる」
✅ 体力・集中力・認知機能の向上
長期の入院や活動の低下による心身の衰えを防ぎ、回復を促す
例:「軽い体操や手作業を通じて、体力や集中力を取り戻す」
精神科作業療法の具体的な内容
🔹 創作活動(アートセラピー):絵画、陶芸、書道、手芸、折り紙など
🔹 音楽活動(音楽療法):楽器演奏、歌唱、リズム運動など
🔹 運動・レクリエーション:軽い体操、ヨガ、スポーツ、散歩など
🔹 園芸療法(ガーデニング):花や野菜の栽培、植物の世話
🔹 日常生活訓練(ADL訓練):料理、洗濯、掃除、買い物の練習
🔹 対人関係訓練(SST):コミュニケーション練習、ロールプレイ、集団活動
精神科作業療法で用いられる作業はさまざまです。作業を通じて「できること」を増やし、自信を回復することが精神疾患の回復につながります!
集団療法の実施形態
入院集団精神療法
精神科病院や専門施設に入院中の患者を対象に行われる治療法で、急性期や回復期の患者が生活リズムを整え、社会復帰に向けた準備をすることを目的とします。この療法では、症状の安定化、ストレスの軽減、感情の安定を図るとともに、集団活動を通じて社会性を向上させ、退院後の生活に適応しやすくすることを目指します。
🔹 代表的なプログラム
📌 支持的集団療法
安心できる環境で、気持ちを共有し、支え合う
例:「うつ病患者同士が、自分の気持ちを話す場を設ける」
📌 作業療法
手作業や創作活動を通じて、集中力や生活意欲を高める
例:「塗り絵、手芸、陶芸、園芸療法」
📌 SST(ソーシャルスキルトレーニング)
社会生活で必要な対人スキルを学ぶ
例:「挨拶の練習、買い物のシミュレーション」
📌 心理教育
病気や治療について学び、自己管理能力を高める
例:「統合失調症の服薬管理の重要性について学ぶ」
通院集団精神療法
退院後や症状が安定した患者が外来診療の一環として参加する治療法で、主に回復期や社会復帰を目指す患者を対象に実施されます。この療法では、再発予防のためのストレス管理や症状の自己管理を学びながら、就労支援や対人関係のトレーニングを行い、生活リズムの維持や健康管理をサポートします。また、病気と付き合いながら適応的に生活するためのスキル向上を目指します。
🔹 代表的なプログラム
📌 デイケア
日中の時間を利用して、作業療法・心理教育・リラクゼーションなどを行う
社会復帰の準備として、日常生活スキルを向上させる
例:「午前は軽運動、午後はSSTやリラクゼーションを実施」
📌 リワークプログラム(復職支援)
うつ病などで休職している人が、復職に向けた準備を行う
仕事のシミュレーションやストレス管理の訓練をする
例:「職場復帰に向けた模擬業務やグループディスカッション」
📌 アディクション・プログラム(依存症リハビリ)
アルコール・薬物・ギャンブル依存症の回復支援
断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)などの自助グループと連携
例:「依存症のトリガーとなる状況を回避する方法を学ぶ」
📌 SST(ソーシャルスキルトレーニング)
退院後の社会生活を円滑に送るための訓練
例:「職場や学校でのコミュニケーション練習」
📌 家族支援プログラム
患者の家族が病気について学び、適切なサポートを行うための支援
例:「統合失調症の患者を持つ家族が、病気との向き合い方を学ぶ」
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
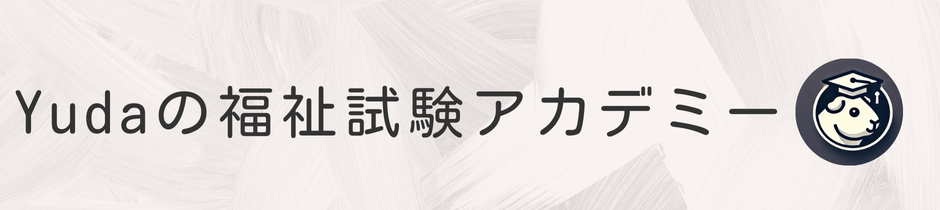
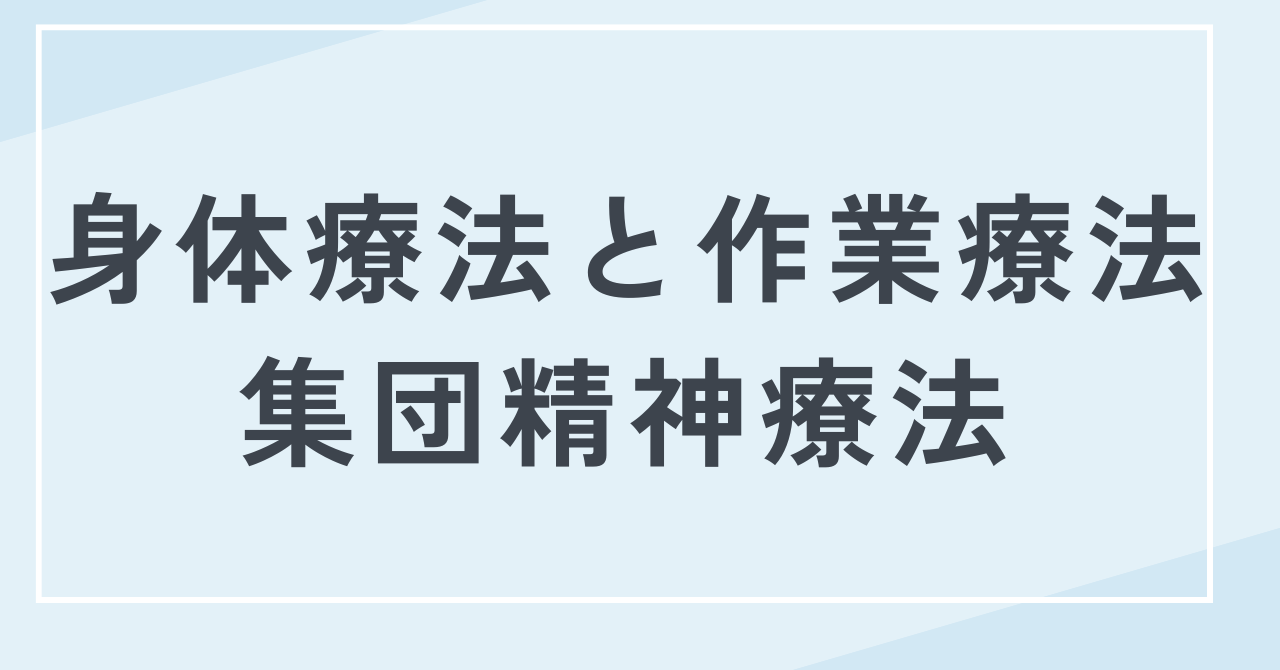
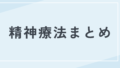
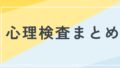
コメント