これまで試験対策の記事しか作成していませんでしたが記事作成に時間がかかるのとモチベーションが上がらないという方向けに志向を変えて、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士の資格を取得した私が、それぞれの資格を目指したきっかけや背景、勉強への向き合い方について振り返ってみました。
同じように受験を考えている方のヒントや励ましになれば嬉しいです。
それぞれの資格を目指したきっかけ
社会福祉士
福祉の世界を志すきっかけは、大学の進路を決めるときでした。せっかく親に学費を払ってもらい大学に行かせてもらうのだから、何らかの資格を取得して意味のある進学にしたいと思っていました。
漠然と「人の役に立つ仕事がしたい」という気持ちと、親が福祉関係の仕事をしていたことから、社会福祉士という資格の存在を知り、取得を志しました。
社会福祉士の受験勉強は、試験の約10か月前、大学4年生の4月ごろからゆるやかにスタートしました。とはいっても、莫大な試験範囲と、大学3年間で全く身についていない知識。当然やる気は起きません。
8月くらいまでは「やっているのか、やっていないのか分からない」、全く身についていない勉強法でした。
しかし、私にはどうしても社会福祉士に合格しなければならない理由がありました。
それは、前年に母親が社会福祉士国家試験に合格していたことです。
母は、当時フルタイムの正社員としてショートステイの相談員として働きながら、家事をこなし、通信制大学で学び、寝る間も惜しんで勉強していたようです。
一方の私はというと、大学4年の単位を取り終え、ゆるい卒論とバイトだけ。時間を持て余す一人暮らしの大学生です。
母親には多少の実務経験があるとはいえ、ここで自分だけ不合格となれば、合わせる顔がありません。
「社会福祉士の合格率は30%(当時)で、範囲も広くて難しいから…」という言い訳は通用しないわけです。
8月に実家へ帰省した際に発破をかけられ、9月から本格的に試験勉強を開始。無事に合格することができました。
※具体的な勉強法については、次回の記事で書こうと思います。
国家試験に合格できたことは、自分にとって大きな転機だったと今振り返って思います。
この資格があったからこそ、介護職から未経験で地域包括支援センターに転職でき、多様な実務経験を積むことができています。
「資格よりも実務経験」と感じることは多いですが、そもそも資格がなければその職に就くこともできなかったわけで、やはり資格は大事だと感じます。
また、あのとき一生懸命勉強した経験は、自分の中でも貴重でした。
恥ずかしながら、それまであまり勉強してこなかったので、大学4年生が人生で一番勉強した時期だったと思います。
努力して結果が出たという成功体験ができたのも大きかったです。
もし仮に不合格だったら、「自分はやるべきときにやれない人間なんだ」と、自分にレッテルを貼ってネガティブ思考の悪循環に陥っていたかもしれません。
社会福祉士の国家試験は1年に1回しかありません。
不合格であれば、「1年間ずっと試験のことが頭によぎりながらズルズルと働き、中途半端な試験勉強をする」そんな未来が想像できます。
もちろん人それぞれ事情は違うと思いますが、「試験勉強をちらつかせながら生活する」というのは、やっぱり苦痛です。
合格を目指すのであれば、試験日を照準に定め、そこで合格するに越したことはないと思います。
介護福祉士
大学時代に重度訪問介護のヘルパーをしていたこと、そして新卒入社した有料老人ホームでの実務経験があったことで、受験資格を得ることができました。
結果的には、合格してすぐに転職してしまったため、「介護福祉士の資格を活かして!」という働き方はできませんでしたが…。
そもそも社会福祉士の資格を持ちながら介護職に就いたのは、就職活動の時点で社会福祉士に合格できる自信がなかったからです。
就職した老人ホームは、民間企業の中では比較的大手だったこともあり、将来的なキャリアアップを見据えて志望しました。
しかし、社会福祉士に無事合格したことで、
- 資格を活かした仕事がしたい
- 直接介護よりも、相談援助職としてキャリアを積みたい
- 今のまま働いていても、いつそのチャンスが来るかわからない
- あと、変則勤務や夜勤は嫌だ(笑)
そう感じるようになり、わずか10か月で転職を決意。
でも、その決断ができたのも、「社会福祉士の資格を持っていたから」こそでした。
精神保健福祉士
現職は高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターです。高齢者だけでなく、そのご家族や関係機関など多くの方と関わる必要があります。特に大変な困難ケースと呼ばれる相談も一定数あります。
また、解決すべき課題が1つではない場合も多くあり、
- 家族に精神疾患のある方がいる
- いわゆるゴミ屋敷
- 8050問題
- 身寄りがまったくいない
- 経済的に困窮している
などが挙げられますが、その背景には精神的な課題が絡んでいるケースも多く見られます。
「これは精神疾患に関する知識や制度を、もっとしっかり学ばねば」と感じ、精神保健福祉士の取得を目指しました。
地域包括支援センターでは、虐待対応やケアマネジャーの後方支援も行うため、幅広い知識と柔軟な対応力が求められます。
そのためのスキルアップとして、精神保健福祉士は非常に役立ちました。
実際に勉強してみて感じたのは、「実務経験は最強!」ということです。
地域包括支援センターで働くなかで、制度や仕組みに関する理解が自然と深まっており、
過去問を解いてみたら全く勉強していない時点でも合格圏内に入っていたほどです。
もちろん、きちんと勉強もしましたが、社会福祉士のときのように「何がなんだかわからない」状態ではなく、実務を通じて得た知識が試験内容にリンクしていて、勉強していて楽しいとさえ感じました。
専門科目だけの試験というのも大きな要因ですね。
まとめ
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士と、それぞれの資格を通じて得られた経験や視点は、仕事だけでなく自分自身の人生にも意味があるものになっているなと感じます。
めちゃくちゃ自分語りしてしまいましたがこの記事が、これから資格取得を目指す方の背中を少しでも押すことができたら嬉しいです。
次回は、実際にどうやって勉強したのか、具体的な勉強法について書いていきます。
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)


試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
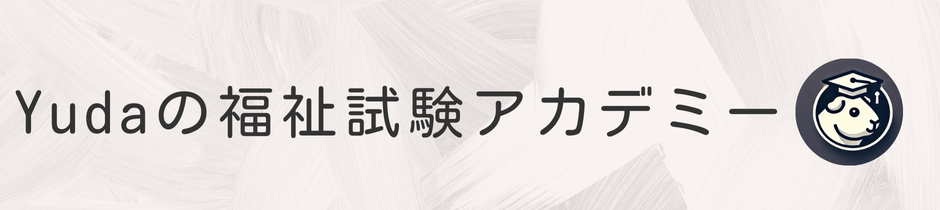
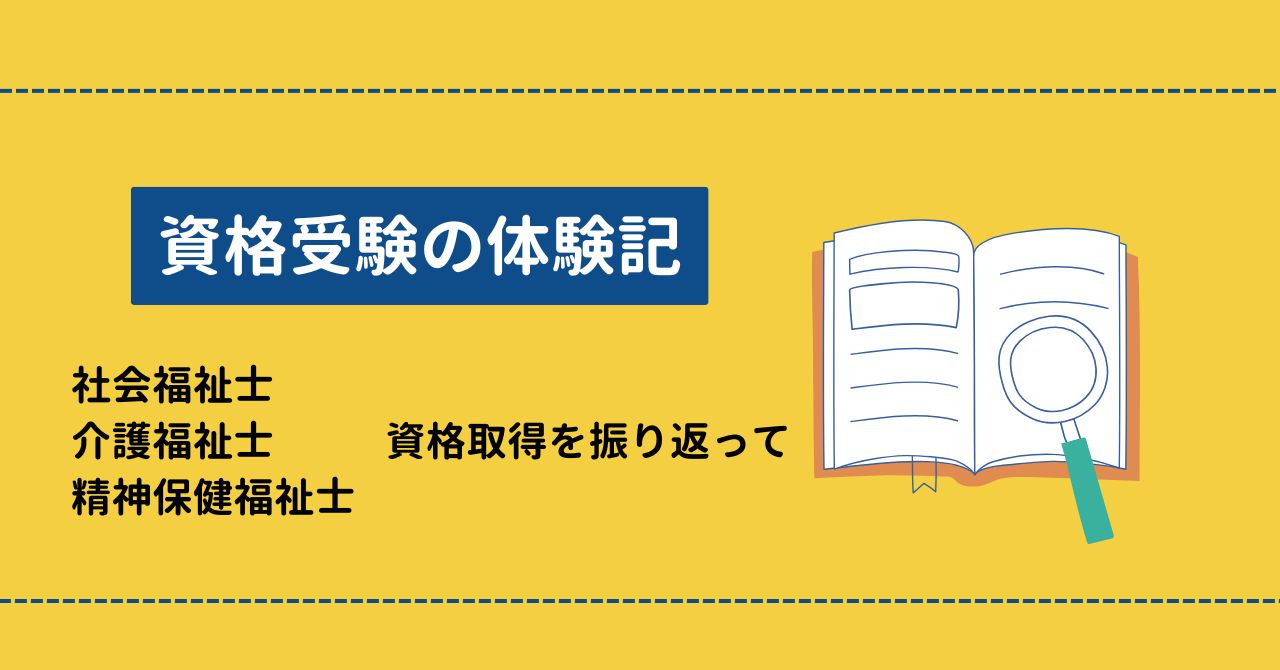
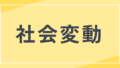
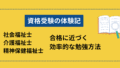
コメント