学校
不登校
定義
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席したもの(ただし、病気や経済的な理由によるものを除く)
フリースクール
不登校やひきこもり、発達障害などの理由で学校に行けない子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設です。
いじめ防止対策推進法
定義
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
- 制定年:2013年6月公布、9月施行
- いじめの禁止:児童等は、いじめを行ってはならない
いじめ防止のための対策組織
学校は,当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,当該学校の複数の教職
員,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等
の対策のための組織を置くものとする。(第22条)
対象となる「重大事態」
学校や設置者は、以下のいずれかに該当する場合、重大事態として速やかに調査を行う義務があります。
✅ 重大事態の2つのケース
- 生命・心身・財産に重大な被害がある疑いがあるとき
→ 例:自殺未遂、精神的ダメージ、金銭の搾取など - いじめが原因で相当期間欠席している疑いがあるとき
→ 例:いじめを理由に数週間〜月単位の不登校
■ 対応の流れ
- 学校または設置者は、速やかに調査組織を設置
- 質問票やその他の方法で、事実関係を明らかにする調査を行う
- 調査結果を踏まえ、同種の事態の再発防止策を講じる
主な教育に関連する法律
教育基本法
日本の教育に関する最も基本的な理念や目標を定めた法律。
すべての国民に対し、人格の完成を目指す教育の理念や機会均等の原則などが明記されています。
学校教育法
幼稚園から大学までの学校制度や教育課程の構造について定めた法律。
義務教育の範囲や特別支援教育、学校の種類と設置基準などが規定されています。
学校保健安全法
学校における健康診断・感染症対策・安全確保などの保健管理体制について定めた法律。
心身の健康保持や事故防止に関する学校の責任も示されています。
教育機会確保法
不登校や長期欠席の児童生徒のために、学びの機会を保障することを目的とした法律。
フリースクールなど多様な学習の場を認め、出席扱いとする仕組みや支援体制の整備が盛り込まれています。
労働者
ストレス
- フラストレーション:自分の中の欲求や期待といった内的な要因が満たされないことで生じる不満やいら立ちの状態。
- ストレス:外部からの刺激(人間関係や環境の変化など)という外的な要因によって、心や体に生じる緊張状態。
- ストレッサー:ストレスの原因となる外部や内部の刺激や状況のこと。
- ストレス反応:ストレッサーによって引き起こされる身体的・心理的・行動的な反応。
- コーピング:ストレスに直面したときに、それに対処しようとする行動や思考のはたらき。
- レジリエンス:ストレスや困難な状況に直面したときに、それを乗り越え回復する力。
問題焦点型コーピング
ストレスの原因となっている問題そのものを解決しようとする対処方法です。
状況を変えることでストレスを軽減することを目的としています。
例 ・上司との関係に悩んでいる → 異動を相談する
・課題が多くてつらい → スケジュールを見直す、手順を工夫する
情動焦点型コーピング
ストレスに伴う感情を和らげたり受け止めたりする対処方法です。
問題の解決ではなく、自分の気持ちの整理や落ち着きを目的とします。
例:・つらい気持ちを信頼できる人に話す
・音楽を聴く、泣く、気分転換する
燃え尽き症候群(バーンアウト)
仕事に強い情熱を注いだ人が、心身の疲労や無力感を抱えて意欲を失う状態のことです。
福祉・医療・教育などの対人援助職に多く見られ、感情の枯渇や人への冷淡な対応、達成感の低下などが特徴です。
ストレスチェック制度
〇対象事業所:常時50人以上の労働者がいる事業場 → 実施義務あり(年1回以上)
〇ストレスチェックの実施者
医師・保健師→無条件
看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理士:一定の研修を修了した者
〇結果の通知(本人に通知)
原則として事業者に結果は提供されない(本人の同意が必要)
〇高ストレス者への対応
本人が希望すれば産業医との面接指導を受けることができる(義務ではない)
労災保険
労災とは
業務中や通勤中に起きた負傷、疾病、障害、死亡などに対して補償を行う制度です。
- 保険者:国
- 対象者:原則として、すべての労働者が対象(正社員・契約社員・パート・アルバイトを含む)
※事業主は対象外
補償の対象となる災害
- 業務災害:仕事中や仕事が原因で起きた災害・疾病(例:工場での事故、過労によるうつ病)
- 通勤災害:通勤途中で発生した災害(例:通勤中の交通事故)
【精神障害の労災認定の3要件】
① 対象となる精神障害であること
- 原則として、ICD-10に基づく精神障害(F3:気分障害、F4:神経症性障害など)
- 発達障害やアルコール依存など、一部の疾患は除外
② 発症前おおむね6か月以内に、業務による強い心理的負荷があったこと
- パワハラ、長時間労働、重大なトラブル対応など
③ 業務以外の要因による発症ではないこと
- 家庭内トラブルや私生活上の問題など、業務とは無関係な強いストレスが主因でないこと
リワーク支援
うつ病などで休職した労働者が、再び職場に復帰できるように支援するプログラムのことです。
主な目的
- 生活リズムの回復
- 就労に必要な集中力・対人スキルの再構築
- 復職への不安軽減と自信の回復
- 職場復帰後の再発予防
実施機関
- 医療機関(精神科クリニック、病院)
- 地域障害者職業センター
- 就労移行支援事業所 など
主なプログラム内容
- グループワーク・認知行動療法
- 職場想定訓練(模擬作業や報連相の練習など)
- ストレスマネジメントや体力づくり
- 医師や産業医、職場との連携支援
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
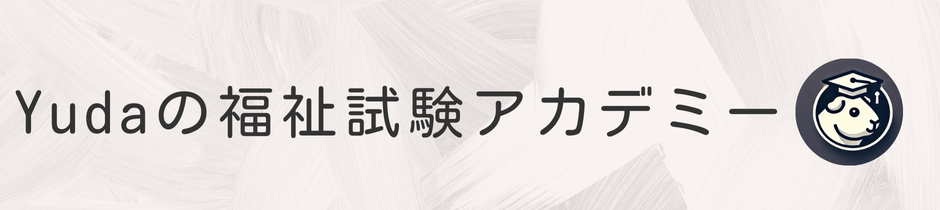
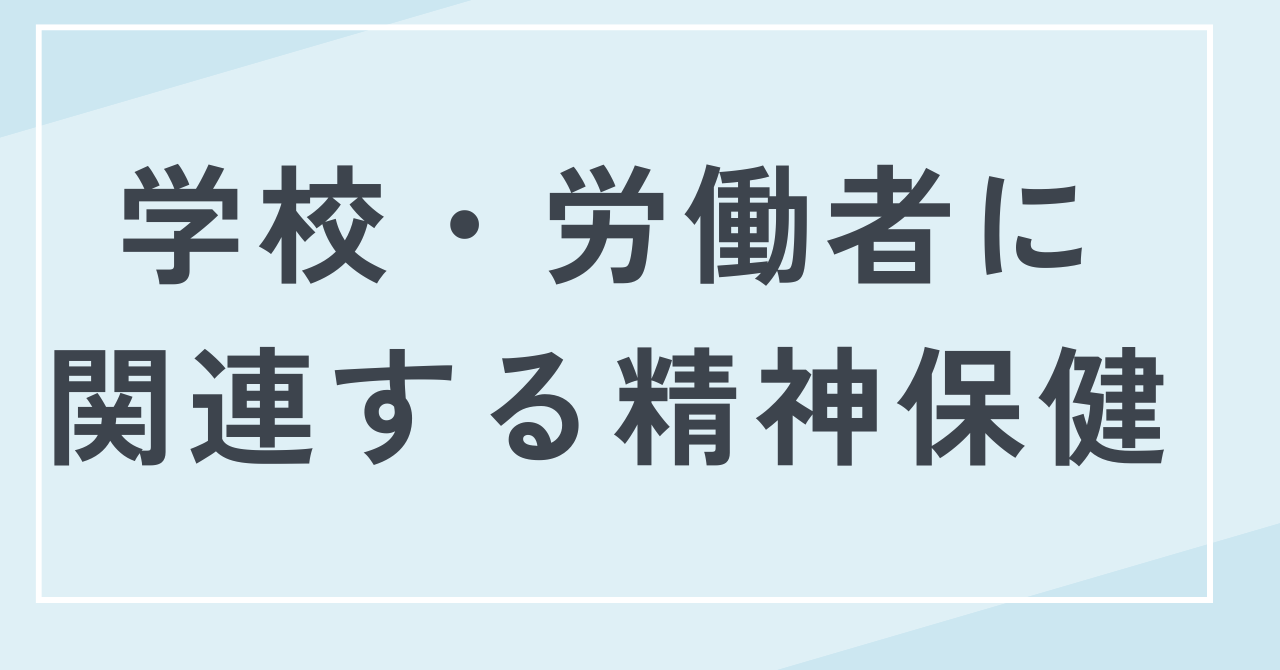
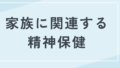
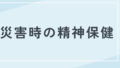
コメント