骨
骨は、体を支える・守る・動かすという基本的な働きに加え、血液をつくる・カルシウムを蓄えるといった重要な役割も担っています。
成人のヒトの体には、約206個の骨があります。骨の数には個人差があり、例えば、肋骨や椎骨の数が異なる場合があります。新生児の骨は約350個ありますが、成長の過程で骨が融合し、数が減少します。
骨の役割
- 支持:体の形を保ち、内臓の位置を固定する。
- 保護:脳(頭蓋骨)、心臓や肺(胸郭)など、重要な臓器を守る。
- 運動:筋肉と連動して体を動かす。
- 造血:骨の内部にある骨髄で、赤血球や白血球などの血液成分をつくる。
- 貯蔵:カルシウムやリンなどのミネラルを蓄え、必要に応じて血液中に放出する。
代表的な疾患
- 骨粗しょう症:骨の密度が低下し、もろくなって骨折しやすくなる疾患。
- 骨折:強い衝撃などによって骨が折れたりひびが入った状態。加齢や骨粗しょう症がリスク要因になる。
骨折しやすい部位
大腿骨頸部:太ももの付け根にある部分で、高齢者の転倒による骨折の代表。寝たきりの原因にもなりやすい。
橈骨遠位端:手首の骨の近くで、転んで手をついたときに折れやすい(コーレス骨折)。
脊椎:背骨の圧迫骨折が多く、特に骨粗しょう症のある人に起こりやすい。
筋肉
筋肉は、体を動かす、姿勢を保つ、内臓を動かすなど、生命活動に欠かせない働きをする組織です。体の約40%を筋肉が占めています。
筋肉の種類
- 骨格筋:自分の意思で動かせる筋肉。手足や体を動かしたり、姿勢を保ったりする。関節をまたいで骨についており、筋収縮によって運動を生む。
- 平滑筋:内臓や血管の壁にある、自分の意思で動かせない筋肉。胃や腸の動き、血管の収縮などを自動的に調整する。
- 心筋:心臓を構成する筋肉。自分の意思とは無関係に、休まず収縮して血液を全身に送り出す。
代表的な疾患
- 筋ジストロフィー:筋肉が徐々に弱くなり、筋力が低下していく遺伝性の疾患。
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS):筋肉を動かす神経が障害され、筋力が徐々に低下していく進行性の神経疾患。
血液
血液は、酸素や栄養素を全身に運び、老廃物を回収し、体を守る働きを持つ重要な体液です。心臓のポンプ作用によって全身を循環しています。
血液の主な成分と役割
- 血漿(けっしょう):水分を多く含み、栄養素やホルモン、老廃物などを運ぶ液体成分。
- 赤血球:酸素を肺から体中の細胞に運び、二酸化炭素を回収する。
- 白血球:細菌やウイルスなどの病原体と戦い、免疫の働きを担う。
- 血小板:出血したときに血を固めて止める。止血作用に関わる。
代表的な疾患
- 貧血:赤血球やヘモグロビンが不足し、酸素が十分に運ばれなくなる状態。めまい、息切れ、疲れやすさが起こる。
- 白血病:白血球が異常に増殖し、正常な血液細胞が作れなくなる血液のがん。
眼
眼の主な構造と役割
- 角膜:目の一番外側にある透明な膜。光を取り入れ、眼の中に屈折させる。
- 水晶体(レンズ):厚さを調節することでピントを合わせ、網膜に鮮明な像を結ぶ。
- 虹彩:瞳孔の大きさを調整し、目に入る光の量を調節する。
- 網膜:光を受け取る細胞が集まっており、視神経を通じて脳に情報を送る。
- 視神経:網膜で受け取った視覚情報を脳に伝える神経。
代表的な疾患
- 白内障:水晶体が濁って視界がぼやける疾患。高齢者に多い。
- 緑内障:眼圧の上昇などにより視神経が障害され、視野が欠けていく疾患。放置すると失明の危険もある。
耳
耳の主な構造と役割
- 外耳:音を集めて鼓膜へと伝える部分。
- 中耳:鼓膜が音の振動を受け取り、耳小骨を通じて内耳へと伝える。
- 内耳
蝸牛:音の振動を電気信号に変えて聴神経を通じて脳へ伝える。
三半規管・前庭:体の傾きや動きを感知し、バランスを保つ。
代表的な疾患
- メニエール病:内耳の異常により、めまいや耳鳴り、難聴が繰り返し起こる疾患。
- 難聴:音が聞こえにくくなる状態。加齢や騒音、病気などが原因。
伝音難聴:外耳や中耳の障害により、音が内耳に届かない状態(例:中耳炎、耳垢栓塞など)
感音難聴:内耳や聴神経の障害により、音は届いてもうまく感じ取れない状態(例:加齢性難聴、メニエール病など)
内分泌器官
脳下垂体
- 成長ホルモン:身体の成長を促進する
- 甲状腺刺激ホルモン(TSH):甲状腺の働きを活性化する
- 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH):副腎皮質にホルモン分泌を促す
甲状腺
- 甲状腺ホルモン:体の代謝を活発にし、エネルギーの産生や体温調節を助ける。
- カルシトニン:血液中のカルシウムを減らす働きがある。
- 副甲状腺ホルモン:骨や腎臓に働きかけて、血液中のカルシウムを増やす。
副腎
- 副腎皮質:
- コルチゾール:ストレスへの対応、代謝の調整
- アルドステロン:水分・塩分バランスを調整
- 副腎髄質:
- アドレナリン・ノルアドレナリン:心拍数や血圧を上げる(交感神経系と連動)
膵臓(ランゲルハンス島)
- インスリン:血糖値を下げる
- グルカゴン:血糖値を上げる
性腺
- 精巣:テストステロン(男性ホルモン)
- 卵巣:エストロゲン、プロゲステロン(女性ホルモン)
松果体
- メラトニン:睡眠と覚醒のリズム(概日リズム)を調整
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
Yudaの福祉試験アカデミー
ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは、自らの経験から精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士などの国家試験対策として活用できる一問一答問題を中心に投稿していきます。【チャンネル主】Yuda重度訪問介護のヘルパーや介護付き有料老...
試験対策おすすめ書籍(PR)

社会福祉士国家試験過去問解説集2026: 第35回-第37回完全解説+第33回-第34回問題&解答
出題基準に基づく第37回試験を含む過去5年分の国家試験を解説。35~37回試験は選択肢ごとに正答に至るまでの道筋を丁寧に解説した。33・34回試験は問題と解答を掲載。試験対策として手にしたい最初の1冊。出題傾向の把握や実力試しに最適。マーク...

この1冊で合格! 社会福祉士 精神保健福祉士 テキスト&問題集 【共通科目】 2025-2026年度版
◇◆大好評、重版!◆◇大人気「カリスマ社会福祉士」がつくったオールインワン型最強教材、誕生!福祉・医療分野における人気の国家資格「社会福祉士・精神保健福祉士」。著者は、ほぼ独学で福祉系国家資格にスピード合格したスキルをもとに、ブログやYou...
試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
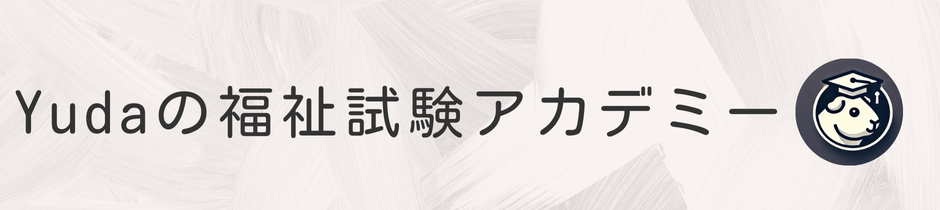
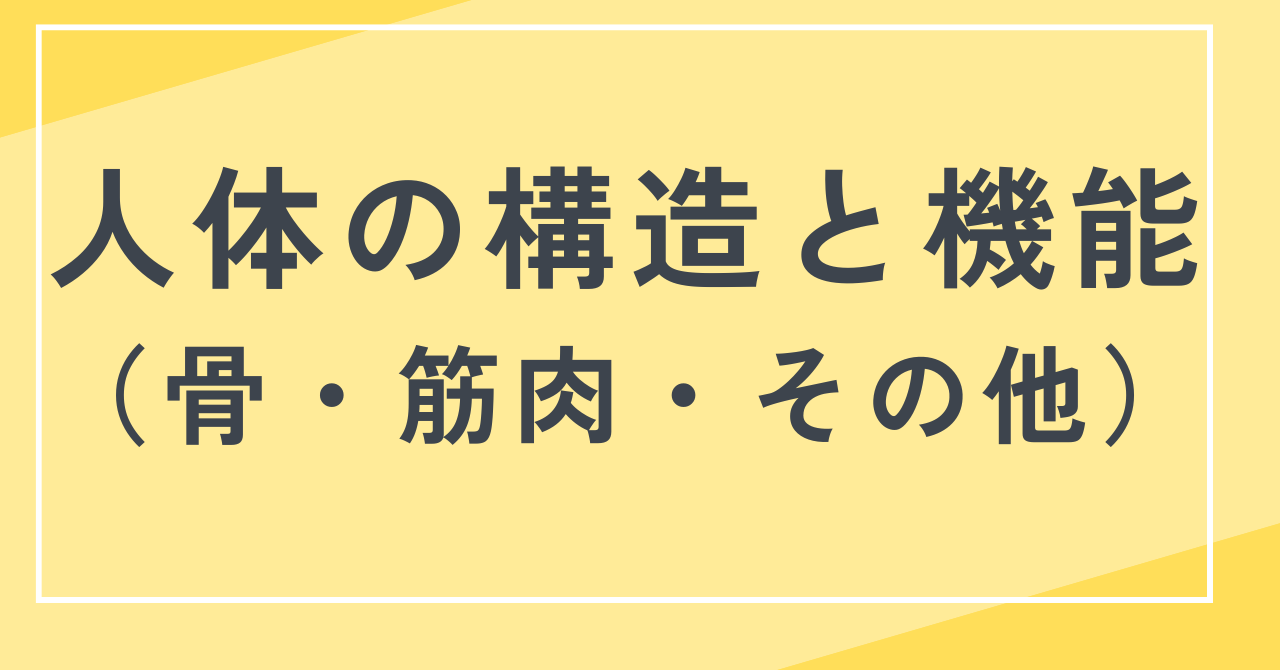
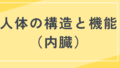
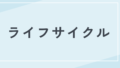
コメント