てんかんは、脳の神経細胞が過剰な電気活動を起こすことによって、様々な発作を繰り返す慢性の神経疾患です。
原因による分類
てんかんは、発症の原因によって3つに分類されます。
特発性てんかん(遺伝性てんかん)
明確な脳の異常が見られず、遺伝的な要因が関与すると考えられるタイプのてんかんです。通常、子どもの頃に発症することが多く、知的発達には影響しないことが一般的です。
症候性てんかん(構造的/代謝性てんかん)
脳の構造的な異常や代謝異常が原因となって発症します。例えば、脳梗塞、脳腫瘍、頭部外傷、脳炎、低酸素脳症などの後遺症として起こる場合があります。
潜因性てんかん
潜因性てんかんは、特発性とも症候性とも判断できないケースを指します。MRIなどの検査では明確な異常が見つからないものの、何らかの要因が関与していると推測される場合に分類されます。
発作の広がりによる分類
発作の広がり方によって、てんかんは「焦点発作(部分発作)」と「全般発作」の2種類に分けられます。
焦点発作(部分発作)
焦点発作は、脳の特定の部位で異常な電気活動が起こるタイプの発作です。この発作には、意識が保たれるものと、低下するものがあります。
- 単純部分発作:意識は保たれたまま、運動症状、感覚症状、自律神経症状、精神症状などが起こる。
- 複雑部分発作:意識が低下し、無意識に口をもぐもぐ動かすなどの自動症(目的のない反復行動)がみられる。
焦点発作は、発作が起こる脳の部位によって症状が異なるのが特徴です。
全般発作
全般発作は、脳全体に異常な電気活動が広がる発作で、意識は必ず障害されるのが特徴です。
代表的なものとして、以下の種類があります。
- 強直発作:全身の筋肉が突然硬直し、意識が失われる。転倒することが多い。
- 間代発作:全身の筋肉がリズミカルにけいれんする。
- 強直間代発作(大発作):強直発作と間代発作が連続して起こり、意識を失ったまま全身が硬直し、その後激しくけいれんする。最も一般的な全般発作。
- 欠神発作(小発作):数秒間意識がなくなり、動作が止まる(特に子どもに多い)。
- ミオクロニー発作:突然体がピクッと動く(筋肉の収縮)。
- 脱力発作:急に筋肉の力が抜け、倒れる。
その他
ウエスト症候群
1歳まで(生後3~11か月頃)に発症する乳児期のてんかんで、点頭てんかん(スパスム)と呼ばれる発作が特徴です。首をガクッと前に倒したり、両手を上げる動作が短時間に何度も繰り返され、脳波にはヒプスアリスミア(不規則な波形)が見られます。 早期治療が重要で、放置すると知的発達の遅れやレノックス・ガストー症候群へ移行することがあります。
レノックス・ガストー症候群
1〜8歳(ピークは3~5歳頃)に発症する難治性てんかんで、強直発作、脱力発作、欠神発作など複数の発作を伴い、重度の知的障害を伴うことが多いのが特徴です。
てんかんの診断・検査と治療
診断
てんかんの診断には、発作の種類や原因を特定することが重要です。そのため、問診・脳波検査・画像検査などを組み合わせて総合的に判断します。一度の発作だけでは診断されず、2回以上の発作が起こるか、脳にてんかんの原因となる異常が確認された場合に診断されます。
治療
治療の基本は薬物療法(抗てんかん薬の服用)で約7割の患者は抗てんかん薬の適切な使用で発作をコントロールできます。ただし、薬だけでは十分に抑えられない難治性てんかんも存在し、その場合は食事療法、迷走神経刺激療法、外科手術などの選択肢が検討されます。
てんかん発作のタイプによって、用いるべき薬が異なりますので、正しく診断することが重要になります。
また、睡眠不足、精神的ストレス、過労、飲酒、薬の飲み忘れなどは発作を引き起こす要因となるため、できるだけ避けることが大切です。
Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!
「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!
また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!
ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!
試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。
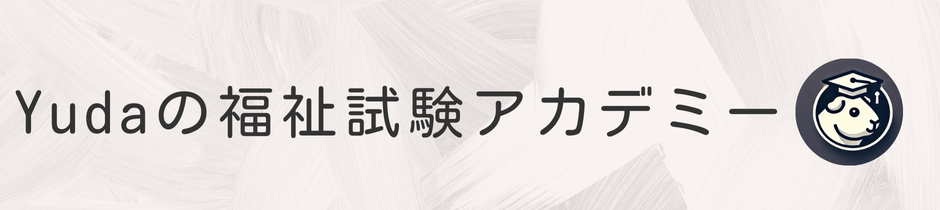
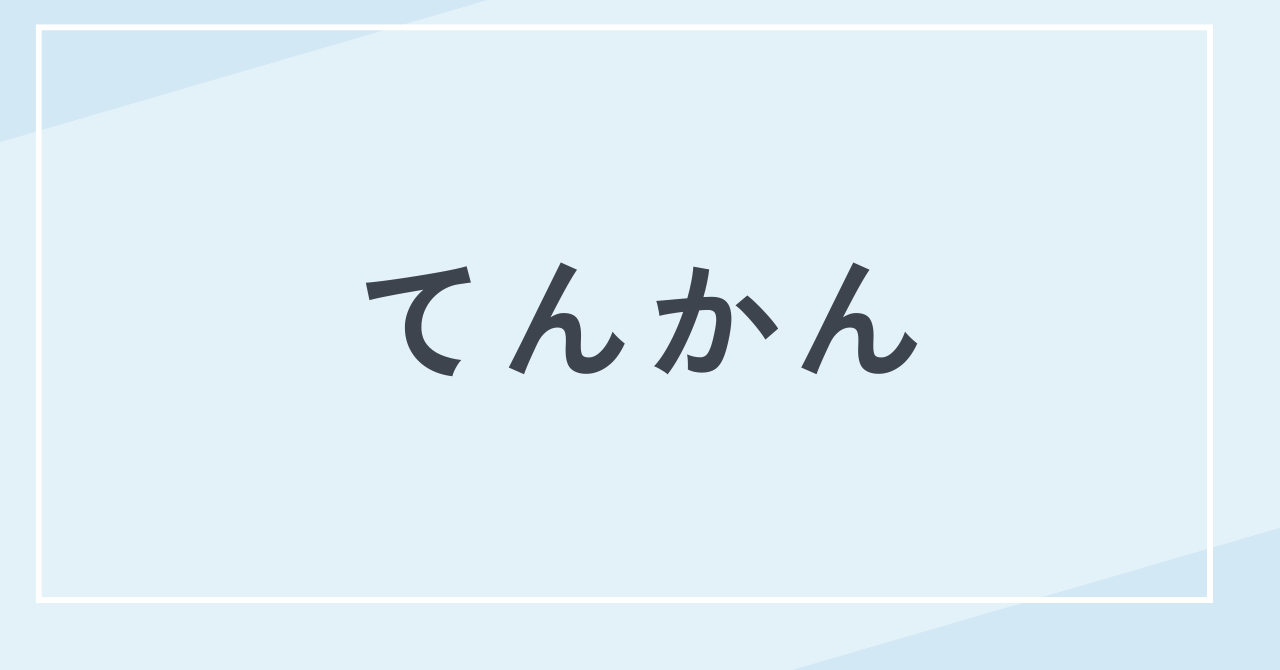

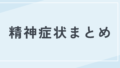
コメント